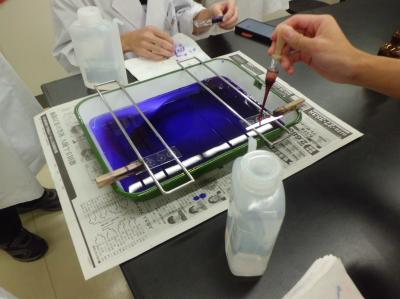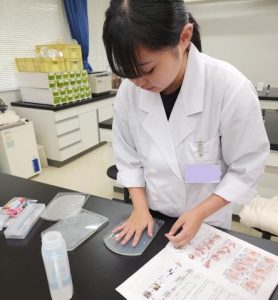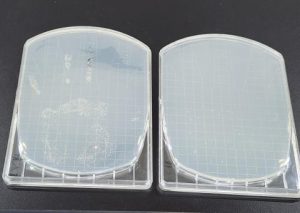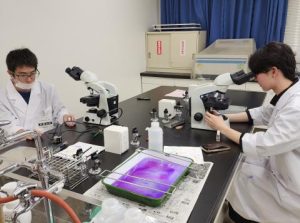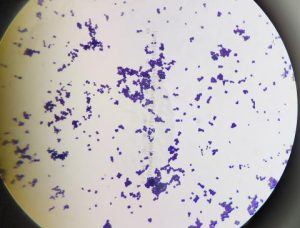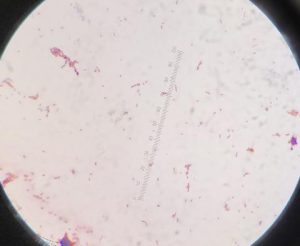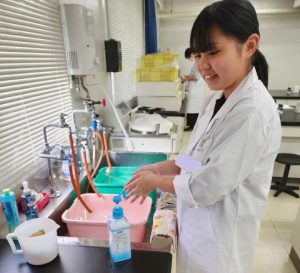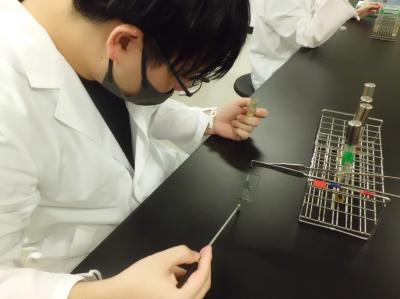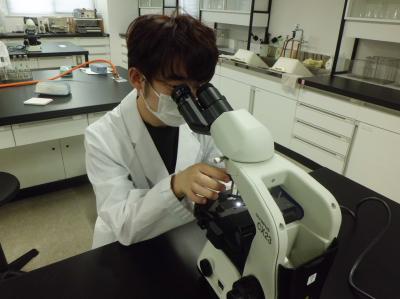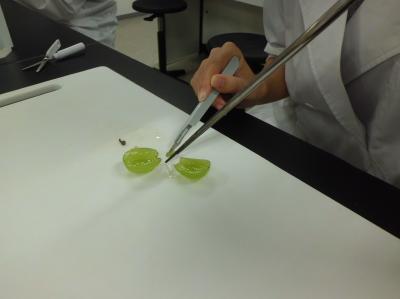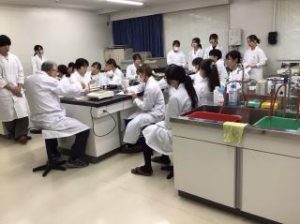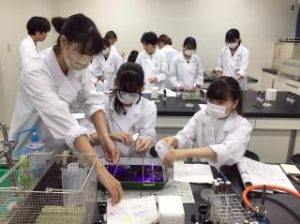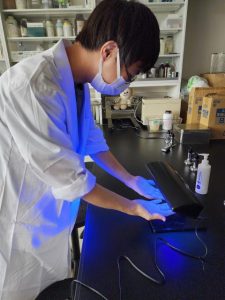みなさん、こんにちは。
愛玩動物看護学科1年生を対象にした、
学外実習を実施しました。
今回の実習の目的は、
「飼育されている動物の生態について知ること」。
また、牧場スタッフの方々のお話を聞いたり、
動物の管理方法などについて見学したりしながら、
牧場についての理解を深めます。
はじめに牧場スタッフの方から、
ウシの生体と飼育管理の方法をご説明いただきました。
次に牧場のご協力をいただき、
新鮮便の採糞を行いました。
ウシを観察しながらそっと近づき、糞回収します。
積極的にサンプリングをしてくれました(^^)/
サンプリングした便は学校に持ち帰り、後日糞便検査を行います。
普段取り扱うことのない、
貴重な動物種の検体を採取することができ、
検査が楽しみですね。