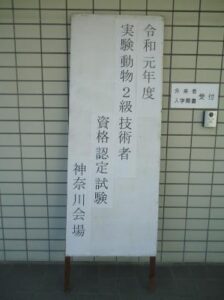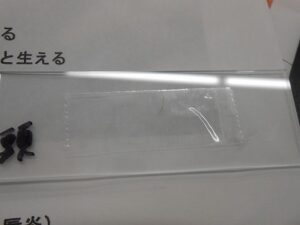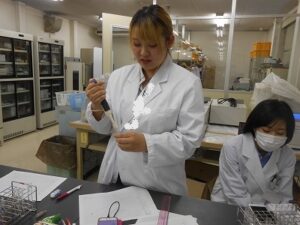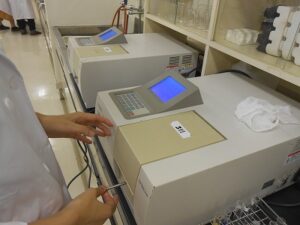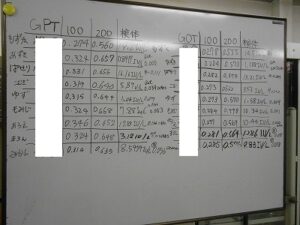みなさん、こんにちは。
少し時間が経過してしまいましたが、DVMs どうぶつ医療センター横浜の説明会を学内で開催していただきました。
社長のYM先生に懇切丁寧なご説明をいただき、参加した学生も刺激を受けたようです。

DVMsどうぶつ医療センター横浜さんには、当学科卒業生のHSをご採用いただいており、2年生の中にも就職を視野に入れて、動物病院実習受け入れをお願いしている者もおります。
YM先生、事務長のAK様、お忙しい中、このような機会をいただき、誠にありがとうございました。
↓↓クリックお願いします