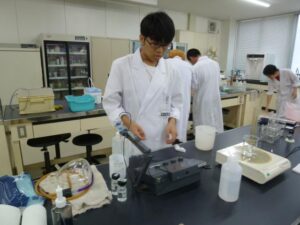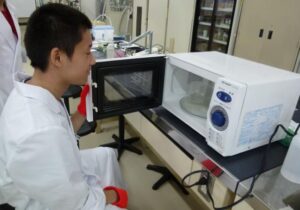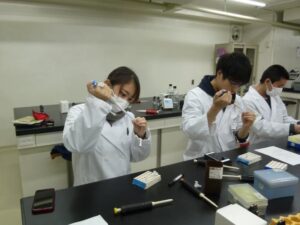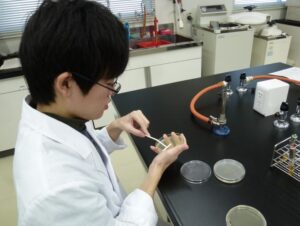みなさん、こんにちは。
動物の眼のお手入れ方法をご紹介します。
今回はメヤニ(眼脂)の取り方についてお伝えします。
犬や猫は人間と同じように眼からメヤニがでます。
動物は人間のように洗顔等をして洗い流すことが自らできませんので、人間の手で定期的に取り除いてあげましょう。
柔らかいコットンにホウ酸水を薄めた液をつけます。
ぬるま湯でもきれいになります。

優しく眼の周りの眼脂を拭き取ります。

アイコームはコームの先が丸く怪我をしにくい構造しています。
頑固な汚れも取れやすいです。
眼脂を取る際は、メヤニの色や量、性質、左右の差を気にすることで、眼科疾患の発見につながります。
よく観察しましょう♪
眼の処置が苦手な動物は多いです。
1人で無理に行わず、誰かに保定をしてもらったり、動物におやつを舐めさせながら行うと、処置をしやすいです♪
↓↓クリックお願いします