みなさん、こんにちは。
今回の生化学実習は、前回分離した卵白アルブミン溶液の定量を行いました。
以前のブログで、DNAの定量をご紹介しました。
操作の流れは、DNAの定量とほぼ同じなので、2年生に少し考えながら実習を行ってもらいました。
まずは、吸収スペクトルの作成です。
分光光度計のモニタ画面です。タンパク質の最大吸収波長は280nmになります。
卵白アルブミン溶液も波長280nm付近に最大吸収波長が出ていますね。

自動でグラフを作成してくれますが、2年生は手書きでグラフを作成します。
これも正しくグラフを書く練習です。


そして、いよいよ卵白アルブミン溶液の定量です。
今回の呈色反応は決まっていますが、反応をどのように行うかは班で相談をして決めてもらいました。


今回の反応では、反応時間がちょっと長いので、休憩中?

反応が終了。反応はしているようだけど、何かおかしい?いつもと違うような・・・・・。

確認をしてもう一度。今度は・・・・・。大丈夫そうです。

反応終了後、測定をして、測定結果から卵白アルブミン溶液の定量を行いました。
2年生のみなさん、いかがでしたか。まだ少し先ですが、この実習では最後に実技試験があるので、
実技試験を少し意識してもらうために、今回は各班で実習内容を考えてもらいました。
無事に卵白アルブミン溶液の定量ができました。2年生のみなさん、おつかれさまでした。
 人気ブログランキング
人気ブログランキング
 自動でグラフを作成してくれますが、2年生は手書きでグラフを作成します。
これも正しくグラフを書く練習です。
自動でグラフを作成してくれますが、2年生は手書きでグラフを作成します。
これも正しくグラフを書く練習です。

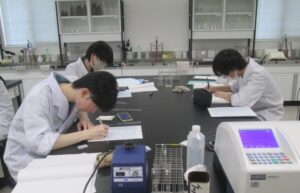 そして、いよいよ卵白アルブミン溶液の定量です。
今回の呈色反応は決まっていますが、反応をどのように行うかは班で相談をして決めてもらいました。
そして、いよいよ卵白アルブミン溶液の定量です。
今回の呈色反応は決まっていますが、反応をどのように行うかは班で相談をして決めてもらいました。

 今回の反応では、反応時間がちょっと長いので、休憩中?
今回の反応では、反応時間がちょっと長いので、休憩中?
 反応が終了。反応はしているようだけど、何かおかしい?いつもと違うような・・・・・。
反応が終了。反応はしているようだけど、何かおかしい?いつもと違うような・・・・・。
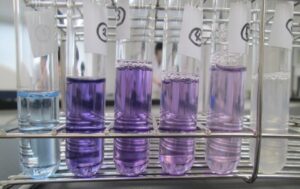 確認をしてもう一度。今度は・・・・・。大丈夫そうです。
確認をしてもう一度。今度は・・・・・。大丈夫そうです。
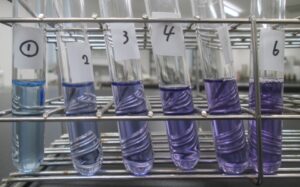 反応終了後、測定をして、測定結果から卵白アルブミン溶液の定量を行いました。
2年生のみなさん、いかがでしたか。まだ少し先ですが、この実習では最後に実技試験があるので、
実技試験を少し意識してもらうために、今回は各班で実習内容を考えてもらいました。
無事に卵白アルブミン溶液の定量ができました。2年生のみなさん、おつかれさまでした。
反応終了後、測定をして、測定結果から卵白アルブミン溶液の定量を行いました。
2年生のみなさん、いかがでしたか。まだ少し先ですが、この実習では最後に実技試験があるので、
実技試験を少し意識してもらうために、今回は各班で実習内容を考えてもらいました。
無事に卵白アルブミン溶液の定量ができました。2年生のみなさん、おつかれさまでした。
 人気ブログランキング
人気ブログランキング
















