みなさん、こんにちは。
2年生の生化学実習では、
ゲルろ過クロマトグラフィーを行いました。
ゲルろ過クロマトグラフィーは、
カラムクロマトグラフィーに分類されます。
ゲルを詰めたカラムで分離された物質を分取し、
分析を行います。
ゲルろ過クロマトグラフィーは、
分子量の違いによって分離されます。
したがって前回のSDS-PAGE法と同様に、
物質の分子量を求めることができます。
今回は、アミラーゼ(タンパク質、酵素)の
分子量を求めました。
実習は、カラムにゲルを詰める作業からスタートです。
詰め過ぎも詰め足らずもダメなので慎重に詰めていきます。


次にサンプルを塗布します。
ゲルを乱さないように驚異の集中力発揮中、
慎重に慎重に!!!!!

溶出液(緩衝液)を追加しながら、
分離された物質を分取します。
色付きは分子量マーカーです。
早速、分離が始まりました。

下から青色、赤色、黄色が確認できます。
黄色がすべて溶出されたら終了です。

今回は、1mLずつ分取しました。

分取後、
吸光度測定と今回は試料にアミラーゼを用いましたので、
ヨウ素デンプン反応を行いました。
分取した溶液は、青色、赤色、黄色の溶液になっています。
これらの溶液の吸光度を測定します。


ヨウ素デンプン反応でアミラーゼの確認をします。
デンプン溶液にヨウ素を加えると青紫色になります。
アミラーゼは、デンプンを分解しますので、
アミラーゼが分取された試験管は、青紫色になりません。

試験管立ての中央あたりは色がありません。
この部分にアミラーゼが含まれます。

吸光度測定とヨウ素デンプン反応の結果から、
アミラーゼの分子量を求めます。


分取した試験管の本数が多く、
吸光度測定も大変でしたが、
グラフの作成も大変そうでした。
青紫色にならない試験管がある程度の範囲でありましたが、
ヨウ素デンプン反応も確認ができました。
ちょっと長めの実習になりましたが、
アミラーゼの分子量も求められました。
2年生のみなさん、ゲルを詰める作業からの実習、
お疲れ様でした。
↓↓クリックお願いします

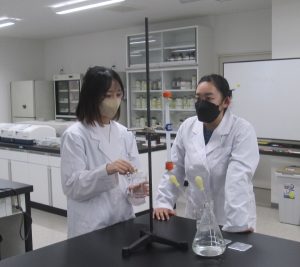
 次にサンプルを塗布します。
ゲルを乱さないように驚異の集中力発揮中、
慎重に慎重に!!!!!
次にサンプルを塗布します。
ゲルを乱さないように驚異の集中力発揮中、
慎重に慎重に!!!!!
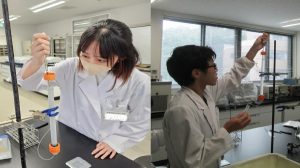 溶出液(緩衝液)を追加しながら、
分離された物質を分取します。
色付きは分子量マーカーです。
早速、分離が始まりました。
溶出液(緩衝液)を追加しながら、
分離された物質を分取します。
色付きは分子量マーカーです。
早速、分離が始まりました。
 下から青色、赤色、黄色が確認できます。
黄色がすべて溶出されたら終了です。
下から青色、赤色、黄色が確認できます。
黄色がすべて溶出されたら終了です。
 今回は、1mLずつ分取しました。
今回は、1mLずつ分取しました。
 分取後、
吸光度測定と今回は試料にアミラーゼを用いましたので、
ヨウ素デンプン反応を行いました。
分取した溶液は、青色、赤色、黄色の溶液になっています。
これらの溶液の吸光度を測定します。
分取後、
吸光度測定と今回は試料にアミラーゼを用いましたので、
ヨウ素デンプン反応を行いました。
分取した溶液は、青色、赤色、黄色の溶液になっています。
これらの溶液の吸光度を測定します。

 ヨウ素デンプン反応でアミラーゼの確認をします。
デンプン溶液にヨウ素を加えると青紫色になります。
アミラーゼは、デンプンを分解しますので、
アミラーゼが分取された試験管は、青紫色になりません。
ヨウ素デンプン反応でアミラーゼの確認をします。
デンプン溶液にヨウ素を加えると青紫色になります。
アミラーゼは、デンプンを分解しますので、
アミラーゼが分取された試験管は、青紫色になりません。
 試験管立ての中央あたりは色がありません。
この部分にアミラーゼが含まれます。
試験管立ての中央あたりは色がありません。
この部分にアミラーゼが含まれます。
 吸光度測定とヨウ素デンプン反応の結果から、
アミラーゼの分子量を求めます。
吸光度測定とヨウ素デンプン反応の結果から、
アミラーゼの分子量を求めます。

 分取した試験管の本数が多く、
吸光度測定も大変でしたが、
グラフの作成も大変そうでした。
青紫色にならない試験管がある程度の範囲でありましたが、
ヨウ素デンプン反応も確認ができました。
ちょっと長めの実習になりましたが、
アミラーゼの分子量も求められました。
2年生のみなさん、ゲルを詰める作業からの実習、
お疲れ様でした。
↓↓クリックお願いします
分取した試験管の本数が多く、
吸光度測定も大変でしたが、
グラフの作成も大変そうでした。
青紫色にならない試験管がある程度の範囲でありましたが、
ヨウ素デンプン反応も確認ができました。
ちょっと長めの実習になりましたが、
アミラーゼの分子量も求められました。
2年生のみなさん、ゲルを詰める作業からの実習、
お疲れ様でした。
↓↓クリックお願いします

















