臨床化学実習~血糖検査(その2)
 ●分光光度計 と セル
試薬盲検(透明)を対照にグルコース標準液(赤色)の吸光度を測定
●分光光度計 と セル
試薬盲検(透明)を対照にグルコース標準液(赤色)の吸光度を測定

 なお、<波長スキャン>により赤色キノン色素の最大吸収波長λmaxは
505nmであること、測定波長と一致していることを確認しました。
*赤色の余色は<色相環>により青緑色なので500nm前後と予測していた
なお、<波長スキャン>により赤色キノン色素の最大吸収波長λmaxは
505nmであること、測定波長と一致していることを確認しました。
*赤色の余色は<色相環>により青緑色なので500nm前後と予測していた
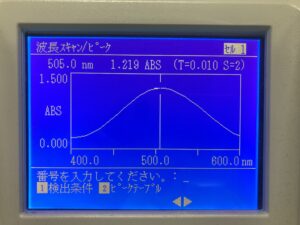
 人気ブログランキング
人気ブログランキング
臨床検査技術学科
ブログ
 ●分光光度計 と セル
試薬盲検(透明)を対照にグルコース標準液(赤色)の吸光度を測定
●分光光度計 と セル
試薬盲検(透明)を対照にグルコース標準液(赤色)の吸光度を測定

 なお、<波長スキャン>により赤色キノン色素の最大吸収波長λmaxは
505nmであること、測定波長と一致していることを確認しました。
*赤色の余色は<色相環>により青緑色なので500nm前後と予測していた
なお、<波長スキャン>により赤色キノン色素の最大吸収波長λmaxは
505nmであること、測定波長と一致していることを確認しました。
*赤色の余色は<色相環>により青緑色なので500nm前後と予測していた
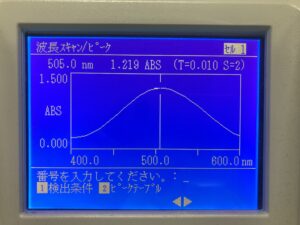
 人気ブログランキング
人気ブログランキング